2009.05.10
vol.12「星ゴキブリ〜後編〜」
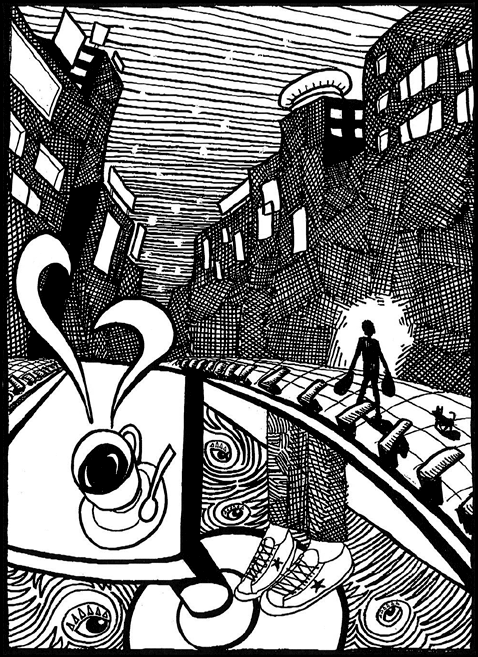
1992年。この年、宇宙開発史上初めての試みがなされた。
人類は初めてゴキブリを宇宙に打ち上げたのだ。
世界初の人工衛星スプートニク1号が打ち上げられてから35年。人類は恐るべき速さで未知の宇宙空間へ進出していった。1961年には世界初有人宇宙飛行を成功させ、1969年には人類が初めて月に到達した。1970年代に入ると火星を始め多くの惑星の接近観測に成功。1981年にはスペースシャトルが初飛行を成功させる。そして1990年代に入ると、宇宙で様々な実験が行われた。1992年のこの年にはアメリカのエンデバー号に搭乗した毛利衛さんが、錦鯉の宇宙酔いの実験を含む37もの実験を行ったことは有名な話だ。
しかし、我々がテレビのニュースや新聞で目にするスペースシャトルや人工衛星の打ち上げは実はほんの一部であり、国家機密によるなんらかの理由で無人ロケットが打ち上げられた例は数多くある。特にアメリカと日本では90年代に入るとあらゆる種類の生物が実験的に小型ロケットに乗せられ宇宙へと旅立った。当然その中には地球に戻れなかったものもあった。
1992年、日本は、あらゆる生物の中でもっとも生命力のあるゴキブリを他の生物と共に宇宙へ送り出したのだ。
しかし、そのいまいましいゴキブリを乗せた宇宙船は発射後すぐに進路から5度ばかりずれ、肉眼で見えるぎりぎりのところで円を描いて急降下していった。そして────消えた。なくなってしまった。炎の瞬きすら見えない。
小惑星プルクシュル。こう名付けたのは地球の天文学者ではない。というのも、地球人はまだこの天体を発見していないのだ。その小惑星に住む住人がプルクシュルと名付けた。我々地球人から見ればその星の住人は宇宙人である。
地球の天文学者は新星や星雲を観察しているときに感光板に紛らわしい光跡を残す小惑星を宇宙のゴミと呼ぶ。直径わずか8分の3海里の宇宙のゴミのひとつ、プルクシュルは、月面を横断するばかりか、地球から10海里足らずまで飛来することがある。しかしこのプルクシュル、光を反射しない。住人が何百万年も前に、光を吸収する暗黒色素で小惑星の表面を塗りつぶしてしまったからだ。太陽光線を反射しなくなった小さな世界は地球やその他の星の住人たちの目を逃れ軌道上を渡っていった。数百万年の歴史を誇る高度な文明をもった小惑星、プルクシュル。
そこに地球から打ち上げられたゴキブリを乗せた宇宙船が ────
ばかでかいロケットのまわりには、何千というプルクシュル人が群がっていた。一同は唖然としてロケットを見上げた。
「まさか我々の星が発見されたのではあるまいな……」
「いや、機体の損傷から見るにこれは不時着したに違いない」「生命体の反応が出てます。ロケット内に生命体がいる」
「生命反応が出ているのは一体のみだが……」
「支配種族の地球人ではなさそうだ……。おおかた実験動物を打ち上げたんでしょう」
「そんなとこだろう。とにかくこの生物の精神を徹底的に調べればなんらかの情報が得られるはずだ。わざわざ地球探査にいかずにすむかもしれん。扉を開けるぞ」
身長わずか1センチ足らずのプルクシュル人がゴキブリを見たときの憎悪感は想像を絶するものだった。何千人もいたプルクシュル人が一斉にその場から逃げ出した。しかし、科学者たちだけは違った。彼らはプルクシュルの未来を背負っているのだ。
「さあ、麻酔を打って実験室に連れて行くぞ!!」
そして、ゴキブリの潜在意識や遺伝子に記憶された心象、事象、知覚したものすべてをサイコグラフでデータ化した。ゴキブリが羽根をもった経緯、触角が長くなった経緯、他生物との争い、子孫を残すために切磋琢磨して歩んできた道のりの他に、あろうことかこのいまいましいゴキブリには人間や地球の多くの情報が蓄積されていた。
地球の多くの情報を得たプルクシュル人はさらに特殊な照射装置を使い、記憶は損なわれないよう知能レベルを微調整して会話を試みた。
プルクシュルの科学者は入れ替わり立ち替わりゴキブリに話しかけた。質問攻めにされたおかげで、このゴキブリの理解力もぐんと深まった。そうしているうちに突然ゴキブリは涙をぽろぽろ流し始めた。仲間のことを思い出したのだ。
「わたくしはいつ地球へ帰れるのでしょうか。人間の都合で宇宙へ打ち上げられ、こうしてこのプルクシュル星へ不時着しましたが……、一緒に宇宙船に乗った仲間や他の動物たちは皆着陸の際に命を落としました……。こんな実験をする人間が憎い……。しかしどうでしょう、わたくしを見たこの星の多くのプルクシュル人も最初憎悪の目でわたくしを見つめました。我々ゴキブリ種族はどこへ行っても憎悪の目で見られます……。所詮実験の道具として利用されるのです。それは我々のこの醜い姿のせいです。しかし……、わたくしはこの姿を創造された神を決して恨みません。わたくしは地球に咲くあの美しい花が大好きなんです。鳥や魚も、命あるものはみんな好きです。我々は醜いこの姿のせいで人間から憎悪の目で見つめられます……、けれどわたくしはあの美しい地球に帰りたいのです……」
確かにこの怪奇な生物をこの星に住まわせるわけにはいかない。そんなことをしたら全国民から非難を浴びることは目に見えている。しかし地球に返してこの星の存在を支配種族の人間に伝えられるのも避けたい。このいまいましくも愛すべきゴキブリをどうしたものか……。科学者、哲学者、物理学者、政治家、軍人、宇宙開発研究員などが皆揃って頭を抱えている。すると突然ひとりの若い科学者がこう言った。
「あの生物に知能レベルを調整できる照射装置の作り方を教えましょう。その後で地球に返します」
「何を言っとるんだ君!! このまま知能レベルの上がったゴキブリを地球に返せば、なんらかの情報が漏れる。支配種族の地球人が我々の存在に気づいたらどうなるかね!? 災いに発展するのは目に見えている!!さっきから何度も言っているではないか!!それに照射装置の作り方を教えるだと!? 何を言い出すかと思えば君は……」
「いえ、その心配はありません。先ほどの実験データではっきりわかったでしょう。あの生物と人間は決して有効的に共存できません。何千年もの間ゴキブリ種族は人間に憎まれ邪魔者扱いされながら人間の手を逃れるように生きてきたのです。彼らは毒薬を使う人間から毎日大量に殺されているのですよ。ですからゴキブリ種族から人間に情報が漏れることは決してありません。照射装置の作り方を教えることに関してですが ──── もちろんゴキブリ種族に限定された照射装置ですが ──── 地球であれだけ邪魔者扱いを受けているゴキブリ種族の知能レベルを上げれば、間違いなく地球に混乱が生じます。そうすれば地球の進歩に遅れが生じます。となれば、数千年はプルクシュルの平和が保てるわけです」
照射装置の作り方を教えられたゴキブリは、身長1センチ足らずの小さなプルクシュル人に深く頭を下げ、宇宙船に乗った。
1996年。あれから4年。進化したゴキブリは地球上で人間の目をかいくぐって子孫を増やしていった。いくら生命力が強いゴキブリでも世界中の家庭で命を奪われる罠を仕掛けられればもはや絶滅の道を辿るしかない。プルクシュル人によって知能を与えられなければ、今日のゴキブリ種族の繁栄はない。人間の気配を感じとり、さらには行動パターンを学び、命を繋いできたゴキブリ。プルクシュル語を話せたゴキブリはさらに進化し、人間の言葉を理解するまでになった。しかし人間とは違い、知能が発達しても支配欲はない。彼らが望むのは子孫繁栄、それだけである。そのために命がけで食料を確保し、命がけで交尾をする。異常なほど繁殖し続けた彼らは、人間界に当然悪影響を及ぼした。この年、アメリカのある州でゴキブリが大量発生し、一部のトウモロコシ畑を壊滅させた。その影響はアメリカの経済界に大きな打撃を与えた。インドのある都市では二機の大型旅客機が接触し、墜落炎上。多くの犠牲者を出したが、大型旅客機の離陸時に紛れ込んだと思われる大量のゴキブリがエンジン部分でなんらかの障害を起こし、衝突に繋がったのではないかと言われている。
日本でもある空港で突然ゴキブリが大量発生し、離陸に失敗した旅客機が炎上した事故があった。その日本では一年前、核燃料の高速増殖炉でナトリウム漏れによる火災事故が発生し、地域の安全性が問われ、管理に問題があると物議をかもした。しかし一年後のこの年、火災事故の調査を続けた職員が、事故の原因は大量のゴキブリの侵入によるものであったと自治体への説明会で発表した……。
──── 誰かが地球のためにゴキブリ問題に立ち向かわなければいけない。
佐藤さんが寝返りをうった。
ぼくは慌てて日記帳を閉じる。シャテニエの時計の針は3時半を指していた。佐藤さんは……。眠っている。壁に留まっているチャバネゴキブリは……。悶えながら小さな卵を容赦なく産み落としている。ポロポロポロポロ次から次に産み落とされる。床にはおびただしい数の卵が転がっている。青白く妙に艶のある小さな小さな卵がまばらに転がっている。吐き気がした。卵は震えるようにわずかに動いていた。よく見るとそれらは卵ではなく幼虫だった。小さな小豆のような筒状の卵鞘が母親ゴキブリの尾についていて、その中からさらに小さな幼虫が次々と床に落ちているのだ。床で青白い幼虫がそこかしこで体を震わせている。血の毛がひいた。気色悪い。幼虫なんて見たくない。ぼくは目を閉じた。目を閉じて、そして考えた。
このおびただしい数の気味の悪い幼虫も成虫になったら子供を産む。産むなと言ってもこいつらは産む。こいつらにその気はなくても、このままいけば地球はゴキブリ種族に支配される。これ以上の繁殖は人類にとって危険だ。繁殖を阻止できるのはぼくしかいない。結局誰かがやらなければいけない。お前らは悪くない。醜いからじゃない。
「星も……海も……我々……ゴキブリも……みんな……神が……つくった……もの……だ……。新しい命……を……授けて……くれた……神に……感謝……します」
母親ゴキブリが息も絶え絶えに言った。そして最後にぼくに神を信仰するかと尋ねた。……そんな気がした。
独り言を話すぼくの声に反応したのか佐藤さんがまた寝返りをうち、ぼくの方に体を向けた。目を開けた。そんな気がした。そんな気がしたが、佐藤さんはまだ眠っている。
足を高く上げ壁に留まっている母親ゴキブリを力いっぱい踏みつける。そいつが床に落ちてからも何度も何度も踏みつけた。ワンスターの靴底についたそいつを振り払い、また踏みつける。そしてトイレにあった殺虫剤を持ち出し、もはや原型を失った母親ゴキブリに向けて執拗に噴射した。床に散らばっている小さな小さな幼虫ひとつひとつにも噴射する。死んだか!?いやまだだ。ボールペンのてっぺんをティッシュで覆い、ひとつひとつ丁寧に潰していく。プチプチッ、プチプチッ。ゴキブリの生命力は恐ろしい。かろうじて生きていた母親ゴキブリは最後の力を振り絞り体をもたげている。命乞いをしているようにも見えたが、ぼくは容赦なく殺虫剤を噴射し、とどめを刺した。すると苦しそうに同じ場所でぐるぐる這いずり回り、母親ゴキブリはやがて動かなくなった。仰向けになった母親ゴキブリの死骸と幼虫のある一帯にまた殺虫剤を噴射した。煙が立ちこめる。何度もむせたがそれでも噴射し続けた。よし。ぼくは地球を守り人類を救った。
視線を感じて振り向くと、佐藤さんが殺虫剤を手にしたぼくを見て固まっていた。
「何してんの……」
ぼくはとっさに佐藤さんから視線を外した。
「臭いよ。なにしてんの!? なにそれ。ゴキブリ!?」
「はい……」
「何やってんだよさっきからさ……」
佐藤さんはゆっくり起き上がり、眉間にしわを寄せてタバコに火をつけた。いまになって殺虫剤の匂いがぼくの鼻の奥に突き刺さる。
「殺虫剤の匂い、店中に充満してんじゃん。なにしてんだよ、やりすぎだろ。ここ飲食店だよ。お客様がそこ座るんだよ」
しゃがみこんでいたぼくを上からキッと睨みつけタバコを一口吸ったあと、それをすぐに灰皿に押し付け、厨房から濡れた雑巾を持ってきて黙ってぼくに渡した。
「すいませんでした」
ぼくはゴキブリの死骸をティッシュで処理し、雑巾で念入りに床を拭いた。けれど拭いても拭いても殺虫剤の匂いはとれない。その匂いはぼくの髪に、顔に、洋服に、コンバースのワンスターにしぶとくついていたに違いない。ぼくを包んでいた幸福の香りをぼくは殺虫剤を使って自ら犯した。
夜が終わろうとしていた。
ふたりでシャテニエを出たあと佐藤さんは「じゃあまた明日ね」と言ってくれたがぼくはただ謝ることしか出来なかった。佐藤さんは純情商店街の方へ、ぼくは駅の方へと別れた。このまま寮に帰りたくないと思ったぼくは駅を越え明るくなりかけた空の下を南の方へと歩き出した。空っ風が吹いて枯れ落ちた葉が舞う。吐く息が白い。佐藤さんは病的なぼくをどんな風に思っただろうか。手をつけずに残ったコンビニの食料を両手いっぱいに持ち、新高円寺にあるファミレスを目指した。店に入る頃にはビニール袋の取っ手は伸びきっていた。
カチッ。
スイッチひとつでぼくは救いようのない世界に簡単に堕ちる。席に座りタバコに火をつけ、水を持ってきたウエイトレスに注文をした。ぼくの体は腐海の中に完全に沈み、内側から徐々に腐り始める。ぼくはまた日記帳を開き、書いてる本人でも理解できないようなことを書きなぐった。それからスイッチひとつで注がれた味気ないコーヒーをゆっくり飲んだ。
椅子の下や壁と床の隙間から視線を感じる。ぼくはあいつらに監視されている。もしかしたらそのときぼくは無性に寂しくて怖くて泣いていたかもしれない。でもだいじょうぶだ、あいつらが活動できなくなる冬はもうそこまできている。それに冬の夜空には星がはっきりと見える。地球が終わる前にぼくは時空を超えこの汚れきったワンスターを履いてあのプルクシュル星に逃げるんだ。
 村井 守
村井 守1978年1月15日生まれ。
やぎ座。O型。山形県山形市出身。中学生の頃のあだ名は「ゴボウくん」。
バンド「銀杏BOYZ」元ドラム担当。

