2007.11.28
vol.5「白い煙」

東京に来たばかりのぼくは初めてのひとり暮らしを楽しんだ。
どうしても輝ける未来を見いだせなかった山形での生活から抜け出し、すべてがそこにあるであろう東京での輝ける生活を始めたぼくは希望に満ち溢れていた。いまだかつて見たことのないたくさんの光景……。いったいどんな冒険がぼくを待ち構えているんだろう……。
不安の要素などまるでなかった。どう転がっていくかわからないこの先の自分のことを考えると楽しくてしょうがない。
将来にたいする不安すら当時のぼくには実体のない期待と希望をもって受け入れられた。
今でもはっきり覚えている。東京に向かう新幹線の窓から見た、青く透き通った空に浮かぶ白い煙に包まれた東京を。
ぼくのひとり暮らしは専門学校で将来の自分や家族のために生きるための技術を身につけることが目的ではない。
この魔法の煙の中でたくさんの冒険をし、たくさんの夢を見ることだ。
バイトもせず、時間を持て余していたぼくは授業を終えるとすぐに高円寺駅前へ繰り出した。山形にはないたくさんの古着屋や古本屋、レコードショップ……。一通り店を回った後は喫茶店に入ってミルクと砂糖をたっぷり入れたコーヒーを飲みながら物思いにふけった。
別の日には新宿へ行った。東口に立ったぼくは、あまりの人の多さに驚いた。
押し合いへし合い体を密着させながらも、どこかはるか遠くへ意識を飛ばし、互いに目を合わせないよう宙を見つめるたくさんの人を乗せた朝の通勤ラッシュ時の満員電車にも衝撃を受けたが、それ以上だった。
これほど多種多様の人間を同時に見たことはいまだかつてなかった。
たくさんの人、人、人を見てはいちいち驚き、注意深く観察した。
背筋をピンと伸ばし、正確な歩幅で歩くスーツを来た中年のサラリーマンが、背中を丸め、だぼだぼのズボンを引きずりながらタバコを口にくわえてプカプカ煙を出して歩くドレッドヘアの若者と談笑しながら並列して歩く様に自分の目を疑った。
そしてモデル顔負けの抜群のスタイルと美貌をもった女性があちらこちらで平気な顔をして歩いている……。いやもしかしたらほんとのモデルさんだぞ!?
なのにだーれも彼女たちを見つめない。あたかもこれが日常かのように。
おや…。
上下カールカナイの派手なジャージを着た少年グループがタバコを吸いながらたむろしてるではないか……。悪そうなのが10人くらい……。おっかねえ。実家の近所のだだっ広いコンビニの駐車場に夜になると必ずたむろしてた少年グループよりだいぶ風貌が恐ろしい……。どの家でも夜はコンビニに行くなって言われてたくらい彼らは恐れられてたはずなのに……、誰もが近寄れなかったはずなのに、ここ新宿では人が彼らの前を平気で横切って行く。よく見るとそこから1メートル圏内に立ち、平気な顔をして待ち合わせをしている女性までいる……。その女性のすぐ後ろでは浮浪者がワンカップを飲みながら平気でゲップをしている……。
危険じゃないのか……。
みんな平気な顔して…。
これが新宿の日常なのか……。
なんなんだこの街は…。
どうもぼくが住んでた世界とはまるっきり違うようだ……。
世界は大変なことになっているんだ。
これが現代なんだ。
目の前に見えるいまだかつて見たことのない光景……。
……!!
これが東京なんだ!!!!
そして今まさにぼくはぼくが望んだ通りの東京に紛れもなく住んでいるんだ!!
人混みに身をまかせ、少し歩くと見たこともない巨大な横断歩道に出た。右に目をやると大通り沿いには空を支えているかのような巨大なビルの柱がびっしり立ち並んでいる。信号待ちをしてるたくさんの人達をのみこむこの新宿の巨大なビル群はいったいどこまで続いているんだろう…。
そんなことを考えながらやはり人混みに流されるがままにぼくは歌舞伎町へと歩いて行った。
こんな調子で日々を過ごしたその頃のぼくには、街で見る何もかもが新鮮で、そのひとつひとつにこれが東京なんだ、と胸のうちでもっともらしくうなずき、そこに立っている自分に喜びを感じた。
この春に東京に出てきた山形の友達と会うこともとても楽しみだった。学校でのこの一週間の出来事や真新しい東京の光景や体験したこと、ひとり暮らしの失敗談などを頭の中で整理しながら、オレンジ色や黄色の電車に揺られ友達の住む街へ行く度に、まるで遠足にでも行くかのように胸が躍った。
改札口を出て、友達の待つロータリーへと足早に歩く。日差しのいい春の光を全身で浴びながら、会えば話はつきることがなく、同じ故郷を出てきた者同士から見た東京を共有し、時間があればあるだけ話していた。
大抵は友達の家に行き、しばらく話をすると近くの公園に移動して缶コーヒーを飲みながらまた話した。しとしきりお互いの報告が終わると大抵は女子の話になる。学校で好きな娘ができたか、可愛い娘がいるか、その娘はどんな服を着ているのか……。
ぼくは高円寺と新宿の女子層の違いや、そしてもちろんモモちゃんの話もした。
山形の友達のひとりで、武蔵野美術大学に通っていた岩城は大学から2分のアパートに住んでいたため、武蔵野美術大学の女子の話で盛り上がると実際に大学へ行き、女子大生を観察した。
だだっ広い校内の中庭ではスケボーをする学生や油絵を描く学生、彫刻を制作する学生、一見よくわからないが何やら現代アートらしきものを制作している学生がいたるところにいた。
山形では見たこともないようなモダンで際立った服を着た学生が目立つ。岩城はそういう際やかな形や色をした服を着た女子に熱くなり、ぼくはそういう娘と連みながらもそれとは対照的にGパンにボーダーのTシャツ、の上に地味な色のガーディガンを羽織っているようなこの学校では一見地味に見える女子に熱くなった。
そしてついには学生食堂まで行き、おしゃべりにふける女子大生を観察しだした。ぼくは、すっかりこの大学の学生になったつもりで得意げにタバコをふかしながら女子を眺めた。
しばらくすると見知らぬ男子が標準語で岩城に話しかけてきた。それまで「んだず、んだず」言ってた岩城は、なんの気負いもなしに「そうだよねぇ」と標準語で受け答えしている。
どうやら岩城にはもう大学の友達ができているようだ。「こいつ山形の友達、すげぇオナニーが大好きなの。面白ぇ奴だよ。」なんて紹介され、ぼくも図にのって挨拶替わりに「小指と親指だげでこすっとキモヂいんだず」と言うと、真剣な顔つきで発せられる突然の東北訛りに岩城の友人は声を大にして笑った。
岩城はその友人に、あそこに座っている女子たちは知り合いか、と聞いた。知り合いなら紹介してもらうつもりでいるようだ。
岩城はもう東京で友達が出来ていた。そしてさらにその輪を大きくしようとしている。そのことにぼくは焦りを感じた。ぼくはといえば、標準語を話すのが怖いあまりになるべく同じ学校の生徒とは会話をしないようにしていた…。
山形の友達とそういう時間を過ごしたあとにひとりで乗る帰りの電車は淋しかった。頭が勝手に友達とぼくを比べようとする。
明日こそ何かあるんじゃないか、もうとっくに心の準備はできている、明日こそぼくを東京の白い煙が飛びっきりのワンダーランドへ運んでいってくれるんじゃないか、そう思っていた。
……けれどそんなことはあるはずなく、毎日が昨日と同じ一日の繰り返しだった。
また明日から学校だ。目的なしに入った学校での授業にも身が入らない。周りの生徒にどう馴染むかばかりを考えているわりには、なんの進展もないまま一日が終わる。だんだんとぼくはこの学校に馴染むことをあきらめようとしていた。
そしてついにこの学校でのもうひとりの自分を作り上げた。
無口で存在感のない、没個性的な生徒。一学年約100名、ぼくの所属するデザイン科は40名にも満たないこの小さな学校で存在感を消すことは容易ではなかったが、休み時間は学校内の図書館へ逃げこむなどしてなるべく授業中以外での他生徒とのコミュニケーションを避けた。そこで適当に画集を選び、じっと観ているといつの間にかその作品に吸い込まれ、そのときだけが息苦しさから逃れることが出来た。
美術大学に比べたら小さい図書館だったが、中世美術から現代アートまでの美術本、写真集やスタジオボイスなどの雑誌、各種参考書など美術に関するあらゆる書物が所狭しと棚に押し込まれ、美術といえば「印象派」しか知らない田舎者の18歳にとっては充分すぎるほどだった。それに映画のチラシや美術展のチラシ、割引券もたくさん置いてあった。
そのうち休憩時間では読み足りなくなり、借りれるだけ借りて家に持ち帰ってはコーヒーを飲みながらじっくりと丁寧に美術本をながめた。
葛飾北斎の『凱風快晴』に酔いしれ、クリスチャン・ボルタンスキーの『D家のアルバム』とにらめっこし、もらえるだけもらった映画や美術展のチラシを眺めては、じっくり吟味し1本に絞ってひとりで街に繰り出した。
最初に東京で観た映画は、渋谷のスペイン坂を上がった左手にあるシネマライズで上映していた『アンダーグラウンド』という戦争映画だった。
渋谷駅に降り立ったぼくは、駅前のスクランブル交差点でたくさんの人に混ざり信号待ちをしていたが、信号が青になったと同時に四方から雪崩れのように人が一気に押し寄せ、一瞬めまいがして倒れそうになり、映画どころではないと思ったが、なんとか受付でチケットを買って観た映画はとても強烈な内容だったことを覚えている。
たまにぼくを「家に来なよ」と遊びに誘ってくれる専門学校の同級生もいたが、アルバイトがあるからと言ってやんわりと断った。
実際にアルバイトを始めたが、お金に困っていたわけではない。ぼくの住んでいた学生寮では朝、昼とご飯は出たし、家賃以外にも最低限の生活ができるぶんだけの仕送りはしっかりともらっていた。
ぼくにとってのアルバイトとはぼくと同級生との間に頑丈な壁を築くための手段だったのだ。
大型百貨店のウィンドウディスプレイのバイトは周に二日、ビルの解体や引っ越しなどの派遣の日雇いの仕事は周に一日。日雇いのバイトのときは、昼の部よりも給料が高い深夜の方を選んでいたので、明け方寮に帰ることになる。門限の夜11時を過ぎると管理人のおじさんは入り口に鍵をかけたが、明け方寮に帰ることは規則には違反してないものの、規則違反以上におじさんの機嫌を悪くし、おじさんのいる朝の食堂へ行くのを避け、学校へも行かずそのままベッドに潜った。
そのバイトを始めたくらいから少しづつ生活のリズムが変わっていった。学校も決まった授業さえ出れば単位をもらえる。ぼくはある時点で安定を失いだした。
山形の友達と会っていないときはどんどん自分の世界にこもっていった。
膨大なひとりの時間。ほんの数ヶ月でこの寮の狭い四畳半の部屋から抜け出したくなった。
あれだけ東京のひとり暮らしに期待と希望をもっていたぼくが、いざ実行してみると淋しくてたまらなかった。専門学校の同級生と話さないのは訛りが恥ずかしい、標準語を話すのが怖いからではなく、どこかで彼らを見下していたぼくは彼らより優位に立っていたかったのだ。そして彼らに空っぽの自分を見透かされるのが怖かったのだ。
実体のない期待や希望は不安に変わり、どう転がっていくかわからないこの先の自分の人生を考えると苦しくてしょうがなかった。恨むべき相手はどこにもいない。この生活を望んだのは他の誰でもなくてぼく自身だ。
あまりにもろい自分が一体なんなのかを考えるようになった。しかし空っぽのぼくが考えてみたところで同じ場所をぐるぐる旋回しているだけで何も答えは出てこない。旋回したまま、宙に浮いた東京という夢の島から自分でも気付かないほどゆっくりとしたスピードで地上へ落下していき、とうとう地面よりもさらにもっと深いところへ落ちていっている気がした。
ショックだった。要するにぼくは自分自身に絶望していた。実家を出て東京に来さえすれば誰かがぼくにたくさんのチャンスを与えてくれると思っていた。
ぼくは早くも東京の白い煙に全身を包まれ、自分の居場所を見失っていた。
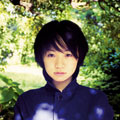
CD「光」発売中!!
M1.光
M2.ナイトライダー
発売日 11月21日(水)
定価 1,050円(税込)
発売元 初恋妄℃学園
![]()
 村井 守
村井 守1978年1月15日生まれ。
やぎ座。O型。山形県山形市出身。中学生の頃のあだ名は「ゴボウくん」。
バンド「銀杏BOYZ」元ドラム担当。

